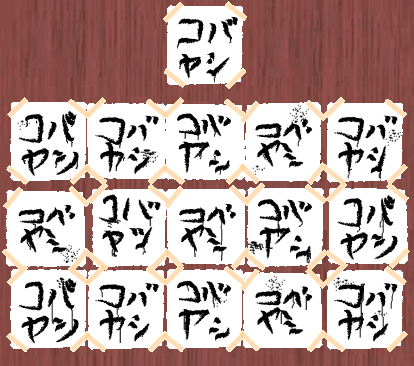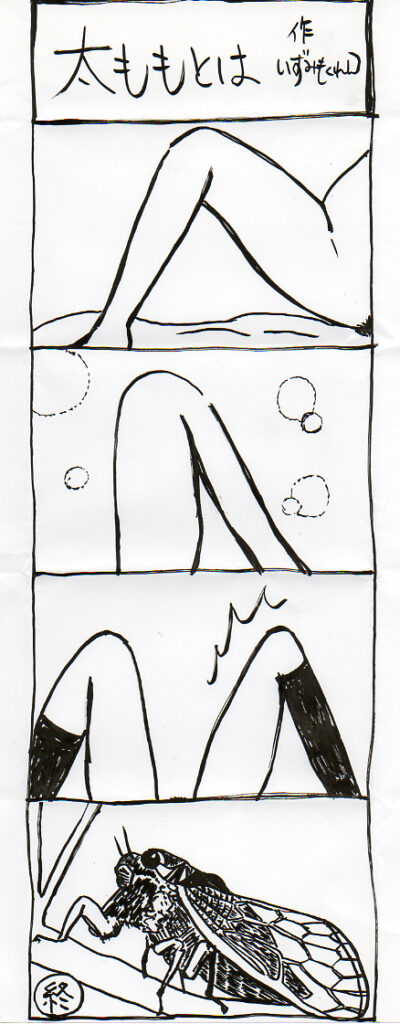(2006年5月の作品)
午後から「大人計画」の芝居を観るために、ひとりぷらりと下北沢本多劇場へ。
終演後、連れ立って語らいながら劇場の階段を下りて散っていく若者たちを横目に、観劇後のすがすがしい感動をもう少しこの地で味わっておきたいと思い、駅前のドトールコーヒーに入った。
アイスコーヒーを飲みながら、劇場でもらった作品のチラシや、ほかの劇団のフライヤーの束に見入っていると、となりの席に、てろてろとした安物のアロハシャツを羽織った金髪のヤンキーらしき兄ちゃんたちが数人座った。
金髪を巨大なリーゼントに仕上げていたり、結い上げた髪にちょんまげのようなものを作って、ほとんど文金高島田みたいになっていたり、大袈裟にイキっているところが青臭くて、庶民的な不良ぶりだった。
金髪ヤンキーたちは、「あの席の男がこっちを見てるぜ」だの、「先輩から集合の電話があった」だの、大声ではしゃぎ倒し、静かな大人の雰囲気のあった店内を、たちまちガキんちょの世界に変えてしまった。
近くの席で静かに新聞や本を読んで落ち着いていた人たちは、それとなく席を移動したり、そそくさと出て行ったりする。
弱ったな、私も離れた場所に移動しようかなと思いつつ、適当な席が見当たらず動けないままでいると、リーダー格らしき金髪アフロヘアの兄ちゃんが、私のほうを向いて話しかけて来た。
「すんませーん、タバコ1本、もらえねえっすかあ?」
赤の他人にもらいタバコを請うなんて、ナメ腐り方がわざとらしい。
「こんな風に他人をナメてる俺」を見せつけてくる、その尊大な劣等感が初対面の人間に伝わっていることに気づいていないところが、青臭さの原因だわと思いつつ、無視するのもマズい気がしたので、努めて動じていない空気を醸しだし、「タバコなんか持ってないわよ」と真顔で答えた。
「そうっすよね。さーせん! 姉さん!」
ガキくさいヤンキー集団を率いた状態で、人を「姉さん」呼ぶなあ!
金髪アフロは笑顔でぺこりと頭を下げた。意外と人懐っこい奴らしい。そうなると、なんだか様子が気になって、バッグに入っていた文庫本に目を落とすふりをしながら、こっそり様子をうかがうことにした。
しばらくすると、金髪ヤンキーたちの向こう側に、ひどくくたびれて色あせたポロシャツにズボン、片足を引きずってひょこひょこと歩く大柄な中年太りの男がやってきて、巨大なジュラルミンケースを「ガン!」と音を立ててテーブルの上に置いた。
浅黒い顔には幾重もの深いしわが刻まれ、眼光は鋭く、顎から喉仏のあたりにかけて15センチほどの裂傷痕がある。
こ、これは……。人殺してるタイプやわー! ジュラルミンケースの中身は、武器と弾薬か!?
はしゃいでいた金髪ヤンキーたちが静まり返る。私は、読んでもいない本のページをめくりながら、これからなにが起きるのか、緊張と好奇心とに支配されて、ただただ目の端に映る「ヤバイ席」の様子に神経を集中させることになった。
私にタバコをくれと言ってきた金髪アフロが、すぐに動いた。
「すんませーん、兄さん、タバコ1本もらえねえっすか?」
おまえ、よう人殺しに声かけるなあ。
感心していると、裂傷痕の男は、胸ポケットからタバコの箱を取り出し、ぶっきらぼうに金髪ヤンキーたちのテーブルに投げた。
ちらっと視線をやると、男の黒ずんだ二の腕には、これまた刃物で切りつけられたような光沢質の白い傷跡が、バッサリと刻まれているのが見えた。
「あざっす! 兄さん! ちなみに、ライターってあります?」
金髪アフロ、なにからなにまで世話になるんかい!
裂傷痕の男は、さらに金色のジッポーライターを取り出して、金髪アフロに手渡しながら、手元で呼び出し音を鳴らしている携帯電話を開いて耳に当てた。途端に、怒号が飛ぶ。
「おう? 適当にやっときゃいいんだろ……アァ? それでいいんだよ。うるせえ! とにかく、あるだけ全部だ。黙って持ってこいや!」
ひいいいい。人殺しの予約電話じゃないのかなあああ?
銃刀に弾薬、あるだけ全部だなんて、どんな大物をヤる気なんだろう。怖すぎる。でももうちょっと観察したい。
すると、世の中をナメすぎて怖いもの知らず状態の金髪アフロが、電話を終えた裂傷痕の男に馴れ馴れしくも近寄って、話しかけ始めた。
「タバコ、赤のマルボロなんっすね! カッコいいっす!」
「ああ? お前ら、いくつだ」
「あ、あの、もしかして警察の人ですか」
「ちげえよ。タバコがカッコいいなんて言うからよ。ガキなんだろ」
「ハタチっす」
「うそつけ。見たところ、高校生だな。まあいいわ」
「あざす!」
うわあ、意外と会話が噛み合っていく。金髪アフロくん、そのぐらいにしておいたほうが身のためかもよと心配はありつつ、もっと絡んで会話を聞かせて欲しい。
「あのっ、俺、実は16っす」
「そうか。そんなもんだろうよ」
「あのっ、今の若者のあいだでは、赤のマルボロとセブンスターがカッコいいんすよ。それは本当なんす。だから、カッコいいっすねって言ったんす」
どこまで純朴なんだ、金髪アフロ。
若者である本人が言う「今の若者のあいだでは」という言葉には、ナメられないように精一杯がんばって「イマノワカモノ」をやろうとしている底知れぬ田舎モン臭さが垣間見える。
わかる、わかるよそのコンプレックス。なにしろ私も同じ田舎モンである。にわかに親しみを覚えた。
すると、裂傷痕の男も何かを感じたらしく、体をくるりと金髪アフロのほうにむけると、黄色い歯を見せてニヤリとしながら饒舌に話しはじめた。
「俺も田舎から出てきた人間だからよ、若い時分は兄ちゃんみたいにツッパッてたなあ。まあ、いまも変わらんまま、年だけ食っちまったけどな」
「え、俺らみたいな金髪とか、してたんすか」
「いやいや、生意気にタバコふかして悪さしてたってことさあ。ま、今でも悪さは変わらんな。兄ちゃんたちは、まだまだかわいいもんだな」
すると、金髪アフロがギッと裂傷痕の男を睨み返し、居丈高な態度を見せた。
「俺ら、けっこうワルっすよ。『鬼露露』って知ってます? キロロ。暴走族っすよ、そこのメンバーなんす。喧嘩も多いし、ヤクザともやりあったこともありますよ。なあ?」
むやみやたらと殺気立つアロハの田舎ヤンキー達は、思い思いの決めポーズで裂傷痕の男にガンを飛ばしている。空気が凍った。
飛び交うのか? 勃発か?
私の心拍数が途端に跳ね上がる。裂傷痕の男は、くしゃっと顔をつぶして大仰に笑った。
「元気のいい兄ちゃんだ。ヤクザとやりあったって? おめえらが睨まれた側だろ。そんな風貌でほっつき歩いてりゃ、目もつけられるわな。ヤクザとは張り合えたのか? 無理だったろ? どうだ。怖い目も見てきたんだろう」
田舎ヤンキーたちが黙りこくった。図星らしい。
「いいか。おめえら自身がそういう格好して、そういう態度を振りまいてるから、ヤクザを『怖い』と感じるんだよ。目ぇつけられて当たり前だっていう自覚が、おめえらの中にあんだろ? それが、怯えなんだよ」
説得力に満ち、ドスのきいたしゃがれ声に、田舎ヤンキーたちの空気が、急に弱弱しくなった。金髪アフロが姿勢を正して、小さな声で打ち明けた。
「はい。ヤクザ、正直怖いっす」
「そうだろう? でもな、聞けよ。ヤクザはな、ヤクザ同士で喧嘩するもんだ。普通の人間には手を出さねえってのが、流儀なんだよ。おめえらみたいなガキに因縁つけて偉そうにしてるやつは、クソだ。弱い者いじめしかできねえ卑怯者なんだよ。どの道、上から締め付けられて、負け犬になる奴だ。そんなもん、怖くねえよ」
土曜の昼下がり、ドトールコーヒー下北沢駅前店にて突如はじまったのは、ヤクザ講座。講師は、裂傷痕のある人殺しっぽい男。いきがった若者たちを諭すような太い声と貫禄ある言葉の数々に、思わず聞き耳を立ててしまったのは、私だけではないようだった。
「でもやっぱ、日本のヤクザさんじゃなくても、B系っていうか、黒人の怖い感じの方とか、いらっしゃるじゃないですか。言葉通じないから、やっぱ怖いっすよ」
「ハハハハ! やられたんか。アメリカ人? 怖くねえよ。まああいつら体デカいしな。おめえら、アメリカ人はみんなピストル持ってるとでも思い込んでるんだろ。それは、先入観てやつだ。反対にアメリカ人に聞いて見ろ。日本人のほうが、むしろ能面みたいで表情が読めないから、怖いって言われてるよ」
なんたる逆転の発想。たしかに、西洋人と比べて感情表現が小ぶりであったり、押し殺しやすい性質のある日本人。文化の違う人々から見れば、恐ろしく感じるのかもしれない。
「なんか、すげえ勉強になるっす」
金髪アフロは、素直に勉強していたのであった。
「アメリカ人は、基本的にクリスチャンだからな。よっぽどでなきゃ、むちゃくちゃなことはしねえ。俺が怖いと思ったのは中国系だな。あっちのマフィアは、見境いなく簡単に人を殺すし、やることもひでえんだ。ま、あまり思い出したくもねえが」
それ以上語らないことが、かえって聞く者の想像力をかきたてていた。
やがて裂傷痕の男は、携帯の着信音を合図に立ち上がり、ジュラルミンケースを持ち上げると、田舎ヤンキー全員を俯瞰して、言った。
「おめえらな、どうやら半分イッちゃってる奴もいるようだが、まあ、まだ素直な目をしてるほうだ。妙な場所うろついて調子に乗ってると、カモにされてロクなことねえぞ。気いつけるんだな」
もはや、ドラマだった。立ち去ろうとする裂傷痕の男にすがって、金髪アフロが言った。
「あ、あの、兄さん、お仕事はなにをなさってるんですか?」
「しがねえ詐欺師さ」
うおおお、なんの詐欺か知らんけど、ドラマとしてはやたらと決まってる!
アロハの田舎ヤンキーたちは、潤んだ瞳にハートマークをぷかぷか浮かせながら、裂傷痕の詐欺師が足をひょこひょこと引きずりながらドトールコーヒーの自動ドアをくぐっていくのを見送っていた。
「じゃ、集会いきますか」と言って、ヤンキーたちもいなくなり、私もドトールコーヒーを出て、下北沢駅前の商店街を散策することにした。すると、前方にジュラルミンケースをぶら下げた裂傷痕の詐欺師の姿を発見した。
なんとなく近寄っていくと、裂傷痕の詐欺師は、着ているシャツ以上にくたびれたババアに、道端で思いっきりどつかれていた。
「あるだけ全部持ってこいって、どこにあるのかわかんないから電話してんじゃないのさッ! このウスノロのバカ野郎め! 人使いが荒すぎるんだよッ! とりあえず、これでいいんだねッ?」
ババアが裂傷痕の詐欺師に叩きつけていたのは、赤いマルボロ、1カートンだった。
(2006年5月の作品)